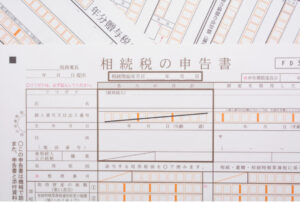人から贈与を受けた場合に、贈与税の申告の義務がある人とない人とがいます。贈与税には基礎控除というものがあり、贈与を受けた財産が基礎控除以下の場合には、申告の義務がありません。また、贈与税には一定の税率があり、贈与の形式や金額によって段階的に定められています。今回は、贈与税申告、基礎控除や税率について解説します。
贈与税の申告義務者とは
贈与税の申告の義務がある人とは、1月1日から12月31日までの間に財産の贈与を受けた人のことです。ただし、個人からの贈与に限り、法人からの贈与は該当しません(一部の法人を除く)。
また、扶養義務者からの生活資金や教育資金のための贈与など一定の贈与に対しては贈与税が課税されません。
贈与税の課税の種類には、暦年課税と相続時清算課税の2種類があります。
暦年課税方式での贈与の場合は、贈与を受けた財産の合計額が基礎控除額の110万円を超える財産について、財産の価格に応じて贈与税が課税され、申告の義務が生じます。贈与を受けた財産の額が110円以下の場合は、贈与税の申告をする必要がありません。
相続時清算課税方式での贈与の場合は、複数年に渡って利用することのできる特別控除額があり、2500万円までは贈与税がかからない仕組みとなっています。2500万円を超える部分については、税率20%の贈与税が課税されます。
なお、相続時には、贈与を受けた財産が相続財産に加算されて計算されます(贈与時の価額で加算されます)。ただし、すでに納めている贈与税がある場合は、計算された相続税から控除されます。
相続時清算課税方式を選択した場合は、基礎控除の110万円を控除することができません。また、贈与を受けた財産の額が110万円以下の場合でも、贈与税の申告が必要となります。
暦年課税制度の贈与税の基礎控除とは
暦年課税制度を利用する場合には、基礎控除というものがあります。基礎控除の額は110万円です。基礎控除は、1月1日から12月31日までの間の1年間の財産の贈与に対して適用されます。同じ人から複数回贈与を受けた場合や、別の人から贈与を受けた場合には、それらを合算した額に基礎控除が適用されます。
贈与税の税率は
贈与税の税率は、一般贈与財産に適用される一般税率と、特例贈与財産に適用される特例税率の二種類があります。
一般税率
一般税率は、特例贈与財産に該当しない一般贈与財産に対してかかる税率です。夫婦間や兄弟間での贈与、親から子への贈与だが子が20歳未満の場合などに適用されます。
一般税率は以下の通りです。例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。
| 基礎控除後の課税価格 | 200万円 以下 | 300万円 以下 | 400万円 以下 | 600万円 以下 | 1,000万円 以下 | 1,500万円 以下 | 3,000万円 以下 | 3,000万円 超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
| 控除額 | ‐ | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
特例税率
特例税率は、特例贈与財産に対してかかる税率です。直系尊属(親や祖父母)から直系卑属(子や孫)への贈与で、その年の1月1日において、20歳以上の直系卑属への贈与の場合に適用されます。
特例税率は以下の通りです。例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します。(夫の父からの贈与等には使用できません)
| 基礎控除後の課税価格 | 200万円 以下 | 400万円 以下 | 600万円 以下 | 1,000万円 以下 | 1,500万円 以下 | 3,000万円 以下 | 4,500万円 以下 | 4,500万円 超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
| 控除額 | ‐ | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
相続税と贈与税の違い
相続税は、亡くなった人の財産を相続した場合の相続財産に対して課税される税金です。相続財産は、相続時にまとめて受け取ることになり、まとまった財産に対して相続税が課税されます。ただし、相続税にも基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人)があります。
対して贈与税は、財産を受け渡す人が生きている間に、財産を受け渡したい人へ贈与する場合の贈与財産に対して課税される税金です。贈与は、生きている間に財産を分割して受け渡すことができます。