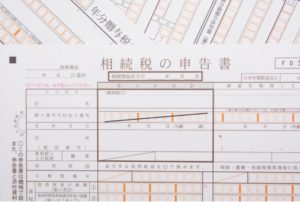代襲相続とは、被相続人が死亡する前に本来相続人となるべき子や兄弟姉妹が死亡等していた場合に、その者の子が代わりに遺産を相続することをいいます。今回は、代襲相続が行われる場合の遺留分の計算、相続税申告における基礎控除額の計算、そして、養子がいる場合の代襲相続、相続放棄が生じた場合の代襲相続など特殊なケースを説明いたします。
代襲相続人が相続するケースとは
代襲相続とは、被相続人が死亡する前に本来相続人となるべき子や兄弟姉妹が死亡等していた場合に、その者の子が代わりに遺産を相続することをいいます。被相続人の子や兄弟姉妹が相続放棄をしても代襲相続にはなりません。被相続人の子を代襲する場合、代襲相続人にも遺留分が認められます。代襲相続人は、相続税の基礎控除算定の人数にも含まれます。養子縁組後に生まれた被相続人の養子の子は、代襲相続人となります。
相続の順位
人が亡くなると相続が開始します。亡くなった人(被相続人)の配偶者は、常に相続人になります。その他の親族は、子(第一順位)、子がなければ、父母、祖父母などの直系尊属(第二順位)、直系尊属が他界していれば、兄弟姉妹(第三順位)が相続人になります。
第一順位の代襲相続
被相続人が死亡したときに第一順位の子が既に亡くなっている場合でも、すぐに第二順位の父母等が相続人になるわけではありません。被相続人に孫やひ孫など(直系卑属)がいれば、直系卑属が相続人になります。このような相続人を代襲相続人といいます。
第三順位の代襲相続
直系卑属も尊属もなく、第三順位の兄弟姉妹が相続人になる場合で、兄弟姉妹が死亡している場合、その子(被相続人の甥や姪)が代襲相続人になります。ただし、直系卑属の場合と異なり、兄弟姉妹から代襲するのは一代に限られ、兄弟姉妹の孫(被相続人の甥や姪の子)は代襲相続人にはなりません。
代襲相続人と遺留分の計算
代襲相続人の法定相続分
法定相続人の相続分は法定されています。被相続人に配偶者と子がいる場合、その相続分はそれぞれ1/2ずつとなり、子が複数いる場合は、1/2を均等割します。配偶者と兄弟姉妹がいる場合の相続分は、配偶者は3/4、兄弟姉妹は1/4となり、兄弟姉妹が複数いる場合は、1/4を均等割します。配偶者がいなければ、子又は兄弟姉妹の人数で均等割します。(ここでは直系尊属がいる場合についての説明は割愛します)
代襲相続人の相続分は、代襲される子や兄弟姉妹(被代襲者)の相続分と同じ割合となります。代襲相続人が複数の場合は、被代襲者の相続分をその人数で均等割にします。
例えば、被相続人に配偶者と子がひとり、孫がふたりいたとします。被相続人の死亡時に子が生存していれば、配偶者と子が相続人となり、その相続分はそれぞれ1/2ずつになります。被相続人の死亡時に子が既に死亡しており、孫ふたりが子を代襲する場合、孫ひとり当たりの相続分は1/4(子の相続分(1/2)の1/2)となります。
次に、配偶者と子がふたりいて、一人の子が他界しており、その子(孫)二人が相続する場合、相続分は、配偶者1/2、子1/4、孫はそれぞれ1/8ずつになります。
代襲相続人の遺留分
遺留分とは、相続人が最低限受領できる遺産の割合をいいます。遺留分が認められる代襲相続人は、被相続人の子を代襲する者だけです。兄弟姉妹を代襲する者には遺留分はありません。
被相続人の子を代襲する者の遺留分は法定相続分の1/2です。上記の例では、代襲相続人である孫ひとりあたりの遺留分は1/8となります。この例で、例えば、第三者への遺贈により代襲相続人の取り分が減り、遺産の1/8に満たない場合、代襲相続人は、遺贈を受けた第三者に対し、足りない分(遺留分侵害額)を金銭で支払うよう請求することができます。
代襲相続人と基礎控除の計算
遺産を相続しても、基礎控除額までは相続税は非課税であり、基礎控除額を超えた分にのみ相続税がかかります。基礎控除額は、3000万円と600万円に法定相続人の数を乗じた金額との合計額と定められています。ですから、相続人の数が多ければ多いほど基礎控除額は大きくなります。
例えば、相続人が配偶者と子ひとりの場合、基礎控除額は4200万円(3000万円+600万円×2)です。もし、子が死亡し、孫ふたりが代襲相続人となる場合は、代襲相続人も法定相続人ですから、相続人の数は、配偶者と合わせて3人になり、基礎控除額は4800万円(3000万円+600万円×3)となります。
このように、代襲相続人が複数いる場合は、代襲がなかったときよりも基礎控除額が増え、相続税額が低くなります。(ここでは、配偶者への非課税枠など、基礎控除額以外の相続税非課税の制度については、考慮しておりません。)
また、死亡保険金や死亡退職金の非課税限度額も法定相続人の数に比例します(非課税限度額は500万円に法定相続人の数を乗じた金額となります)。代襲相続人も法定相続人としてカウントされますので、代襲相続人が複数いる場合は、代襲がなかったときよりも非課税限度額は大きくなります。
相続放棄と代襲相続
被相続人の子や兄弟姉妹が、相続開始のときに死亡している場合に加え、被相続人や他の相続人を殺害したなどの欠格事由があり相続人になることができない場合や、被相続人に対して虐待など著しい非行を行い、被相続人により廃除され相続権を失った場合にも代襲相続が発生します。
これに対し、被相続人の子や兄弟姉妹が相続人になれるにもかかわらず、相続を放棄した場合、その子らが代襲相続人になることはありません。
養子の子と代襲相続
被相続人の養子は子として第一順位の相続人になります。養子縁組後に生まれた、養子の子は、被相続人の直系卑属として、養子が相続人になることができないときは、代襲相続人になります。これに対し、養子縁組のときに既に生まれていた養子の子(連れ子)は、被相続人とは親族関係になく、代襲相続はできません。